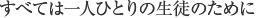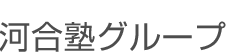西高校問題分析 受験生情報局 | 河合塾Wings 関東
2025年度 西高校の入試問題分析
西の英語
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
リスニングを除くと大問3題で、その構成は対話文が1題と説明文が2題で昨年と同様である。物語文が出題されないのは6年連続である。一方で、今年も昨年同様に理系的な内容のテーマが出題されており、理系分野の出題の傾向が続いている。自校作成問題校の中でも、特に文章量が多い学校の1つであるが、今年度の長文の総語数は3,000語を超えており、非常に長いことが特徴である。しかし、しっかり過去問演習をしてきた受験生にとって、今年度の英文は比較的理解しやすく、また設問も例年の形式を踏襲しているため過去問演習の成果を発揮することができたのではないだろうか。ただし、リスニングを除くと、40分で解かなければならない点は変わらず、設問を解く順番を考えながら読み進めていくことが引き続き求められる。
【2】は日本の高校生とインドネシアの高校生が、海の環境問題について話し合う対話文であった。昨年度は海洋生物にヒントを得た新素材についてのテーマであり、海をテーマにした長文が今年も出題された。各設問は一昨年・昨年度と全て同じ傾向であり、過去問演習による傾向対策をしっかり積んでいれば比較的得点をしやすい問題が多かった。西高校を目指すのであれば、今年度も80%くらいの正解率を目指したい。問2の語句整序問題は、wantやmakeの語法理解に加え、関係代名詞のthatの知識も必要となり、語彙・文法に関する正確な知識が必要になった問題と言える。また、問4は全体の要旨把握と同時に、空所に適切な形に変形して適宜補充する必要があり、品詞・単複など細部に注意しなければならなかった。
【3】は小鳥やアリなどの動物のコミュニケーションの手段について述べた説明文だった。問4の下線部内容把握問題では「仮定法」を用いた文に下線が施された。下線部周辺の内容把握に加え、仮定法の正しい文法理解が求められた問題だと言える。問6の文整序問題については、論理関係を表す語句や代名詞に注意を払いながら解答すべきであった。日常の長文読解演習に置いて、上記語句への意識を高めておく必要がある。
【4】はトルコのボスポラス海峡周辺の交通状況について述べた説明文だった。問4では本文中で説明された海底トンネルの構造の縦断図を選ぶ問題が出題された。本文内容に関する言語情報を、視覚的に表現し直す問題は他の自校作成問題校でも出題されており、過去問演習によるトレーニングが肝要である。また、問6の解答に際して、記述する単語はもちろんだが時制にも注意を払う必要があった。解答時間も限られる中で、正しく解答する力も求められるとなるとやや難度の高い問題とも言える。問7の内容一致問題では、(B)③の選択肢のように本文では直接的に表現されていないものを、本文内容を踏まえ正確に選択できるかが重要であった。本文と同じ表現だから、といった理由で安易に選択肢を判断しないことは言うまでもなく必要な素養である。
本校合格の鍵はやはり「速読力」及び「設問の解答順」である。他の自校作成問題校の過去問題等で時間を測って解く練習を多く積むことで、次第に速読力は身についていく。また、本校の設問の出題傾向として、「内容一致」問題の配点が高いことが挙げられる。リスニングを除いた読解問題で、「内容一致」問題は1問4点(本年度も6問出題され、合計24点)であることに対し、他の設問は1問2点である。他の受験生と差をつけるためには、設問の解答順を考えながら解き、「内容一致」問題を得点できるようになることが望ましい。日頃の読解練習においても、限られた時間の中で内容を正しく理解し、設問の解答順を考えながら解く、ということを常に意識してほしい。
西の数学
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
【1】は例年通り、5題構成の小問集合であった。問1の根号を含む式の計算、問2の2次方程式はいずれも基本的な計算問題なので正確に短時間で処理したい。問3はカードを引いて、文字列を入れ替える確率の問題だったが、同じアルファベットに注意をすることができれば難しくはなかった。問4は代表値を利用する問題で、条件を満たす値を丁寧に吟味する必要があった。問5の作図は一見手間がかかりそうに見えるが、完成図における等しい角に注目できれば、素早く仕上げることができる。全問正解も目指せる大問だった。
【2】は2次関数で、問1は2点を通る直線とx軸の交点の座標を求める基本問題であった。問2は座標平面上での角の大きさを求めるのだが、難度は高くないので、傾きや三角形の辺の長さに注目して途中の記述を書ききりたい。問3は放物線と円の交点の座標を求める問題で、手はつきやすいが、解法によっては途中の計算量や解答時間に差がつく問題であった。
【3】は円周上に頂点がある三角形に関する問題だった。問1は線分の長さを求める基本問題、問2は三角形の合同の証明で、例年の西高校の証明問題と比べると受験生は取り組みやすかったと思われる。問3は四角形の面積を文字式で表す問題で、数値が与えられていれば面積を求めることは容易いが、文字の扱いに慣れていないとミスをしやすいため注意が必要だった。
【4】は連続する正の奇数の和の性質に関しての問題であった。問1は和が平方数になる性質を確認する問題のため確実に正解したい。問2は6個の連続する正の奇数の和が360になる場合の有無を検証する記述の問題だった。西高校の【4】の記述は敬遠する受験生もいるだろうが、今年は難度が抑えられて、取り組みやすくなっていた。過去問の印象で避けてしまうのではなく、手をつけてみることで差がついた可能性がある。問3は連続するn個の奇数の和が2025になる場合の最大のnを求める問題だった。最後の問題で時間的制約もあるが、ここまでの誘導に従えば立式は難しくない。条件を満たすnを吟味する時間があれば正解することも十分可能だった。
難度を見極めながら基本から標準問題を正解する力が必要なのは勿論だが、2025年度の数学は受験生にとって手がつきにくい問題は少なく、例年難度が高くなる後半の小問についても、解法の見通しが立ちやすい構成になっていた。来年度以降の受験生には、「難しい」と決めつけず、まず取り組んでみる姿勢で臨んでほしい。特に【4】については他の自校作成問題校と異なり、整数・文章題なども含めた幅広い単元について準備しておくと良い。
西の国語
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
【1】漢字の読み 8点 【2】漢字の書き取り 8点
【3】小説文 26点 【4】論説文 38点 【5】融合文20点
出題形式・配点共に例年と大きな差異は見られない。ただし、昨年と比較し【4】が約600字、【5】が約1,300字多くなっているので、より効率的な文章の読み方・解き方が必要になる。特に【4】に関しては非常に難解な文章なので、解答に至るまでのスピードが要求される。記述問題としては、【3】問4の70字、【4】問7の200字作文、【5】問4の抜き出し問題となっている。200字作文は「最難問」となっているが、他2問についてはしっかりと対策すれば正答を得ることも可能と思われる。
【1】、【2】(漢字の読み書き)
三字熟語は例年どおりの出題、四字熟語は3年ぶりに出題された。読みは、音読ができればすべて正答を得られるが、「東麓」は普段の生活ではあまり触れない言葉なので、戸惑う受験生もいたと思う。書きは慣用的な表現が多く、受検生の語彙力が試されていると考えられる。四字熟語に関しては、漢字自体は通常の生活ではまず触れない言葉なので、それ相応の対策が必要になる。
【3】小説(砥上裕將「一線の湖」より 約4,600字、前年比+約450字)
水墨画を学んでいる主人公が、小学1年生を相手に学校で特別授業を行う中で、図らずも水墨画の神髄に触れるという内容について書かれている。
記述問題は多少難易度が高い。しかし、傍線部の付近を精読することで対応できる。
他の記号問題は、判別しづらい選択肢を含むものもあるが、心情理解・内容理解をする訓練を積めば高い正解率になると思われる。
映画化・漫画化された作品であり、本年度日比谷高校でも同じ小説から出題されている。
【4】論説文(朝倉友海「ことばと世界が変わるとき」より 約4,600字、前年比+約600字)
文章冒頭に書かれているように、「客観性とはなにか」について抽象的に論じた文章である。
問題傍線部にも抽象度の高い言葉(「身体的存在」「単層性」「重層性」など)が多く使われており、正答を得るためには、文章内容の正確な理解が求められる。特に問3~問5に関しては、根拠とすべき文章が線部から離れていたり、そもそも選択肢が非常に抽象的な表現になったりしているため、理解しづらさを感じた受験生も多くいたのではないかと考えられる。過去問題などで抽象的な文章を読み慣れるとともに、普段の生活の中でも、語句に関して関心を持ち語彙力を高めていく必要がある。
問7には例年どおり200字以内の作文も出題されている。これを書き切るには、上述の抽象的かつ難解な文章・問題に対しての読解・処理能力を高めることが不可欠になる。
【5】融合文(田渕句美子「百人一首 編纂がひらく小宇宙」より 約3,800字、前年比+約1300字)
百人一首に掲載されている和歌の配列について説明した文章である。
全八首の和歌が掲載されているが、その一首一首に詳しく解説が書かれているため、内容理解は比較的容易にできる。その理解を基に解けば、記号問題で満点を取ることも可能だろう。問4に抜き出し問題が出題されているが、根拠とすべき箇所が限定されていたため、字数に注意して読めば正答を得られると考えられる。
お問い合わせ・お申し込み
-
イベント申し込みはこちら
-
資料請求はこちら