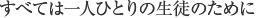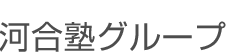都立共通問題分析 受験生情報局 | 河合塾Wings 関東
2025年度 都立共通問題分析
共通問題の英語
難易度の表記
A:解くことが必須
B:80点を取るために解くことが必要
C:他の受験生と差をつけるために解くと+α
D:解けなくても仕方ない(時間内に解かないという判断をしてもよい)
【概状】
大問数…大問4題、小問23問
【1】リスニング(5問 各4点)
A(3問)選択式3問
B(2問)選択式1問 記述式1問
例年同様、問題Aでは2人の短い会話を聞いて答える問題が3問、問題Bではアナウンス(商業施設の館内放送)を聞いて答える問題が2題出題された。昨年と比較して大幅な変化はない。問題BのQuestion2では助動詞canが使われており、答えの可能性となる箇所が2つあるが、質問文後半のキーワードを聞き取れば迷わず正しい方を選ぶことができる。
【2】小問(4問 選択問題4点×3問、英作文12点)
問1と問2共に資料を見ながら対話文を読み解く形式で、例年と変わりないが、問1の文章量が微増した。ただし、解答の根拠が見つけやすく、かつ資料や文中に明記されている情報を用いて選択肢を選べる問題であった(問2も同様)。問3も例年同様、Eメールの文章を読み、その内容について合っている選択肢を選ぶ問題と、そのEメールに対しての返事を条件に従って3文で書く問題だった。今年度のテーマは「より練習したいと考えていること」であった。直前に質問が書かれているため、何に対して答えるべきかわかりやすく、答えやすいテーマである。
【3】対話文読解(7問 各4点)
語数、出題形式共に大きな変更はなかった。傍線部の内容を問う問題が5問、本文の内容に合う適語を選択する問題が2題出題された。傍線部の前後に答えの根拠が書かれており、どれも落ち着いて解いて得点したい問題である。ただし、問3に関しては傍線部の指示語とは関係のない問題だったため、何に対して聞かれているのかしっかり理解したうえで、選択肢を見ていくとよい。
【4】長文読解(7問 各4点)
例年どおりの出題形式で、語数に大きな変化はなかった。傍線部の内容を問う問題が1問、指定された英文を本文の内容に合う順序に並べかえる問題が1問、適文補充が3問、内容一致が2問出題された。共通問題では初めて本文中で仮定法が使われたが、問題を解くうえで直接影響せず、文章量、選択肢の長さ共に昨年とほとんど同じで、過去問題で演習をかさねていれば失点を防ぐことができる大問であった。
【昨年度との比較】
昨年度と比較して、難度は下がり解きやすくなった。語数は大問によっては微増しているが大きく変わってはおらず、新傾向の設問もなかった。このことから、いかに失点を防ぐのかがポイントであると言える。長文の速読トレーニングはもちろん、過去問題の演習量をしっかりと確保することが得点のカギである。
共通問題の数学
難易度の表記
A:解くことが必須
B:80点を取るために解くことが必要
C:他の受験生と差をつけるために解くと+α
D:解けなくても仕方ない(時間内に解かないという判断をしてもよい)
【概況】
大問数…5問 小問数…19題
例年と問題数・配点に変更はなく、中学学習単元から満遍なく出題された。
計算の難易度も例年通りであり、計算ミスを誘うような構成ではなくプロセス(考え方)を重視するような内容であった。
総じて基本的な力を問うような入試問題であったため、普段からケアレスミスを防ぐ練習を積めていたかが高得点へのカギになっただろう。また、一部難問があったため、上位校ではここの成否もポイントになるだろう。
【設問内容】
【1】小問集合(9題 問1~8…5点、問9…6点)
大問2が1次関数の年は、そこで変域を問われることがほとんどないため、小問内に2次関数の変域が含まれることがあり、直近では2021年以来であった。ちなみに角度の問題と入れ替わりなのも2021年と同様。過去、確率とデータの活用が交互に出題されていたが2024入試の箱ひげ図を挟んだ2023年と2025年は連続で確率だった。さらに本年の確率は教科書の基本問題に類題が少ないタイプでもあった。それでも新出単元の問題はなく、全体的な難易度は例年通りと言える。
【2】文字式の利用(2題 問1…5点、問2…7点)
一周期から見抜ける性質を文字に落とし込んで表現させる問題が出された。問1は具体的な数字を代入すれば選択肢から答えを見つけられるため確実に得点したいところ。問2は式変形を利用してa、b、c、dの4種類の文字を2種類にまとめるなど、題意に則するようにうまく式を整えて解いていく必要があり、なかなか方針が見えず苦労した可能性がある。問1の時点で式変形の形が見えていれば、問2も同じ形での表現が可能なのでスムーズに書き進められただろう。
【3】1次関数(3題 各5点)
今年度は「1次関数」からの出題であった。そのためここ数年続いている「2次関数」と「1次関数のみ」が隔年で出題される傾向も変わらず。一次関数の場合は直近の過去問をみても、問1で座標を求め、問2で直線の式を求める形が2019年・2021年・2023年で一致しており、2025入試も同様であった。問3の面積比較も2019年・2023年同様「2倍になるとき」であった(2021年のみ「等しくなるとき」)。非常に傾向と一致しているため、過去問演習を通して解法を熟知していれば難なく解けた一方、苦手意識を残したままでは差がついてしまった大問であった。
【4】平面図形(半円)(3題 問1…5点、問2①…7点、問2②…5点)
半円に関する問題が出された。円の問題は定期的に出題されているが、半円の形が出題されたのは2017年以来。最初に与えられた図は都立入試では珍しく問1の条件に対して正確でない図であったので、見た目で判断しようとすると解答を誤ってしまう可能性があった。しっかりと計算で答えを導きたい。問2①は合同の証明で、合同・相似が交互の出題される傾向は変わらず。問2②の面積比は様々な図形の知識を利用して解く問題で、難度の高いものだった。解ければ他の受検生との差をつけられただろう。
【5】空間図形(直方体)(2題 各5点)
例年、問1は角度や線分の長さなど基本的な問題が出されるが、問1から体積を求めさせられるため計算力が必要な年であった。底辺や高さといった解くための情報は比較的分かりやすいため落ち着いて正答を目指したい。
問2は空間内で斜めに位置している平面図形の求積で、こういった問題を苦手とする生徒は多いだろう。共通問題における求積のパターンは限られているため、問題に直面した際にどの手法で解くのがベストか引き出せるように演習を積んでおくのが望ましいだろう。
【昨年度との比較】
大きく変わった大問はなく、例年の傾向のままであった。一定数選択問題(マークシート)があることも変わらずであったため、解き方が分かっていれば計算ミスによる失点をいくらか回避できたかもしれない。すなわち昨年度までと同様”思考力”に重点を置いており、計算ミスは大目にみるような形式だった。正しい処理ができるかどうか、選択肢から適切な解答を選べるかどうかが問われただろう。昨年度の比較でも書いたが、日頃より公式や解答の棒暗記をせずに「自ら考え立式して解く学習」を行って力を伸ばしていくことは必須であろう。正答すべき問題で確実に正答し、難度の高い問題でどれだけ得点できたかで差がついた入試問題だった。
共通問題の国語
難易度の表記
A:解くことが必須
B:80点を取るために解くことが必要
C:他の受験生と差をつけるために解くと+α
D:解けなくても仕方ない(時間内に解かないという判断をしてもよい)
【概況】
問題数…大問5題 小問25題
【1】、【2】漢字の読み書き
ほとんどの問題が過去に出題のあった漢字の問題であった。都立高校の入試問題では例年過去に出題があった漢字から作問されているので過去問を中心にしっかりと対策をして満点をねらいたい。
【3】小説文(にしがきようこ「アオナギの巣立つ森では」より 約3,000字、前年比+270字)
小学6年生の「ぼく(あおば)」と同級生の梛がアオナギと名付けたアオタカのヒナの巣立ちを見守った後に寂しさをかみしめながらも、葛城さんから夏の山に行かないかという誘いを受け、喜ぶ場面。表現の特徴に関する問題が1問、理由説明に関する問題が1問、心情説明に関する問題が3問出題された。「アオナギ」が巣立つ場面から、葛城さんから山へ行かないかという誘いを受ける場面までの「ぼく」の心情の細かな変化やほかの登場人物たちとの関係に注目して文章を追っていく必要がある。すべて記号問題であったため、ここでもなるべく全問正答をすることが望ましい。
【4】論説文(中田星矢「文化のバトンを受け継ぐコミュニケーション」約3,400字、前年比-680字)
人間の賢さは道具を使うことにあるのではなく、他者からの社会的学習による文化の累積的進化であるという主旨の文章。具体例が多く、それぞれの例がどのようなことを示すための例なのかつながりを理解していなければならない。傍線部の筆者の論拠に関する問題が2問、傍線部の内容理解に関する問題が1問、段落の役割に関する問題が1問出題された。例年通りの形式で、記述問題(200字作文)は「文化を受け継ぎ発展させること」というテーマで、具体的な体験や見聞も含めて書くという内容だった。配点は問5の記述問題が最も高く、ほかの選択問題を解いた後、本文の「伝達による累積的文化進化の促進」という内容をきちんと理解したうえで、自分の体験・見聞を引き出して書くことができるかどうかがポイントになる。
【5】融合文(A河合隼雄・池田利夫「松浦宮物語と藤原定家」B前田雅之「なぜ古典を勉強するのか」約3,200字、前年比-640字)
Aでは『源氏物語』を読むことで、歌を詠む前後の人々の心の動きや状況を学ぶことができるという対話から藤原定家による『古今集』の編集という話題の転換ののち、『松浦宮』における「定家らしくなさ」についての対話がなされている。Bでは『六百番歌合』から見る藤原俊成の『源氏物語』への評価について述べられていた。A・Bで共通して『源氏物語』を歌人必読の書であるという俊成の考えが述べられている。内容把握や発言の役割のほかに文法問題(「ない」の識別)が1問、現代語訳が1問出題されているが、それほど難解な問題ではないため、多くの受検生にとって得点できる問題だといえる。1つの大問に2つの文章がある場合は、それぞれの共通点や関連性を読み取っていくことがポイントである。
【昨年度との比較】
・昨年同様、記述問題は200字作文のみの出題。
・文章量は全体で-1,050字減少し、一昨年なみの文量。
・大きな変更はなく、字数の減少も相まって高めの平均点になることが予想される。
共通問題の理科
難易度の表記
全体の7割 A:解くことが必須
全体の2割 B:80点を取るために解くことが必要
全体の1割 C:他の受験生と差をつけるために解くと+α
D:解けなくても仕方ない(時間内に解かないという判断をしてもよい)
【概要】
問題数:大問6、小問25(各4点)
4分野ごとの問題数:生物6、地学6、物理7、化学6※昨年度と問題数は変わらず
解答形式別問題数:記号選択23(うち計算が必要な問題は6つ、完答8)、記述2※完答が7増加
【設問内容】
【1】4分野からの小問集合
問4に密度、問5に圧力を計算する出題があった。全体的に基礎知識を身につけていれば取り組みやすい問題である。
【2】4分野それぞれのレポートを読んで解く問題
問3で水蒸気量を計算した後に、もうひと計算する必要がある出題があった。この問題は完答の問題にもなっており、正確に問題文を読み解く力が求められる。
【3】(地学)地層や岩石
問3で地層の標高に関する出題があった。都立ではあまり見られない形式の問題であるが、普段から地層のつながりに関する問題などで練習していた受検生とそうでなかった受検生で差がつく問題となった。
【4】(生物)植物の成長と細胞
問2で出題された分裂中の細胞内の染色体の本数を選ぶ問題では読み間違いや勘違いが起こりやすい問題だった。しっかりと読めていれば難度は高くない。大問自体も基礎知識を確認する問題が多く解きやすい大問だった。
【5】(化学)物質の変化
酸化銀と炭酸水素ナトリウムの2つをそれぞれ熱分解する実験から出題された。基礎知識から多く出題された。問3の溶解度に関する問題では計算に必要な数値を読み解くだけでなく、何を聞かれているのかしっかりと理解する必要があった。
【6】(物理)電流と磁界
コイルに流れる電流によってできる磁界に関する問題を中心に構成された大問だった。問4の記述問題では抵抗器を並列にすることでモーターに流れる電流が大きくなること、電流が大きくなったことで磁界からうける力も大きくなることの2点を説明する必要がある問題だった。
【昨年度との比較】
完答の問題が昨年の1題から大きく増えて8題となり、計算を必要とする問題も昨年の5題から6題に1題増えた。
処理に時間がかかる問題が多くなったので、素早く正確に解く力が求められる。
全体的に基本知識を確認する問題が例年同様に多いが、問題文が長く、解くために必要な情報を正確に読み解くのに苦戦した受検生も多かったと考えられる。問題文を要約すれば設問内容そのものは難しくないが、読み間違いや勘違いから失点し、差がつきやすい問題が複数あった。普段から基本事項を暗記するだけではなく、問題文をきちんと理解し短時間で解く練習をする必要がある。
共通問題の社会
難易度の表記
A:解くことが必須
B:80点を取るために解くことが必要
C:他の受験生と差をつけるために解くと+α
D:解けなくても仕方ない(時間内に解かないという判断をしてもよい)
【概状】
・問題数:大問6、小問20(各5点)
・分野別問題数:地理9、歴史6、公民5
・解答形式別問題数:記号選択17、論述3
・記号解答の内訳:四者択一9、二者完答3、四者完答5
【5】
問3 不況時の景気対策で、政府による増税か減税かについては容易に判別がつくが、日本銀行が市中銀行から国債を買い上げる買いオペレーションとその逆の売りオペレーションが、市中の通貨量を減らすのか増やすのかをきちんと理解していないと正解にたどり着かない。
【6】
問2 グラフから国を特定するにはオーストラリアとエジプトの2カ国までは絞れるがそれ以上は判別ができない。文章から国を特定するには「1922年にイギリスから独立した」ことを知っていなければいけないので難度が高い。
お問い合わせ・お申し込み
-
イベント申し込みはこちら
-
資料請求はこちら