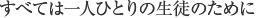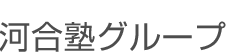国立高校問題分析 受験生情報局 | 河合塾Wings 関東
2025年度 国立高校の入試問題分析
国立の英語
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
昨年同様、長文が2題、小問数が【2】で10問、【3】で9問の設問数であった。
【2】は「効果的な学習方法」に関する対話文。従来のように理系偏重というわけではなく、「産出効果」や「スタンディングミーティング」など、脳科学的に記憶力を良くするための方法が紹介される内容であった。新たな傾向として、問3で脳の活動領域を表すイラストを選択する問題が出題されたが、設問個所の直後に解答の鍵となる文がすぐに見つかるため難易度は低いと考えられる。また、問10の内容一致問題の出題形式が、他の自校作成校で見られる複数の選択肢の中から正しいものの組み合わせを1つ選ぶ形式に変更された。解答を吟味するのに時間がかかるので十全な演習をこなしておきたい。
【3】は典型的な物語文。ハワイに短期留学をした少年が、言葉の壁にぶつかりながらも、ホストファミリーとの交流を通じて自信を取り戻していくもの。英文内容は平易で読みやすいが、昨年よりも語数がやや増加している。問5と問8で条件英作文が出題されているが、どちらも本文の内容を理解する読解力と、本文の表現を置きかえる表現力が試されている。問6では内容不一致の選択問題が出題されたが、解答の根拠となる部分も設問個所に近く、問題文の意図を読み取れればそれほど難しい問題ではない。
国立の数学
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
【1】は例年通り、5題構成の小問集合であった。内容も昨年と同じだが、昨年より少し易化した。「データの活用」の出題は最近のトレンドなので、しっかり準備をしておくべきである。ミスなく全問正解を目指したい。
【2】も例年通り、放物線と直線をテーマとするものであった。問1と問2は確実に正解しておくべき易問。問3は座標平面上の三角形の相似、面積を活用して、点の座標を求める典型問題なので、解法の方針をしっかり記述できるようにしたい。
【3】の今年度は、2年続いた“円”をテーマにした出題がなかった。問1と問2(1)の三角形の合同の証明は正解しておくべき易問。問2(2)は出題者の意図を読み、(1)をヒントにして考える事が優先順位は上ではあるが、この問題のようにいろいろな解法が考えられる場合は、そこに固執する必要はない。
【4】は昨年から引き続き、空間内を動く点に関する出題であった。このパターンの問題を知っているか否かで差がつく問題である。そういう意味では、できる限り多様な問題にあたっておきたい。問2は、解答欄に展開図を載せることで、少しでも着手しやすくしてくれている出題者の配慮も伺えるものの、図形の組み合わせに気づけなければ、相当な難問になるであろう。
国立の国語
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
【1】漢字の読み 10点 【2】漢字の書き取り 10点
【3】小説文 24点 【4】論説文 36点 【5】融合文20点
出題形式や配点など例年と差異は見られない。ただし、今年度は課題文章が例年に比して長いのが特徴である。その課題文章本文に加え【4】論説文では生徒が書いた想定の「レポート」約1,000字を読む必要があった。また、抜き出し問題は適切な部分を見つけるのに時間がかかったであろう。200字作文を含め全ての問題を解き終えるにはかなりのスピードが要求されているが今年度はその傾向がより顕著になったと言える。本校のような難関高を受験するならあらゆる入試問題に解き慣れて量をこなしておくことが必須である。
【1】、【2】(漢字の読み書き)
例年同様に三字熟語、四字熟語が出題された。読み取りの「定款(ていかん=組織の規則文書)」「補填(ほてん=不足分の埋め合わせ)」といった生徒たちにとっては馴染みの薄い語が読めるかどうか。書き取りの「イショクドウゲン(医食同源=日頃の食事は医療同様に健康維持に重要である)」は大人にとっては耳慣れた言葉ではあるが、中学生がこの語を四字熟語の成句として学習する機会はほとんどないであろう。漢字単独の知識として学習するだけでなく、多くの文献に目を通した読書量、経験値による語彙力が求められている。
【3】小説(青山美智子「リカバリー・カバヒコ」第4話『勇哉の足』より 約4,300字、前年比+約1,200字)
小学4年生の「勇哉」が足を捻挫したと嘘をついて駅伝大会への出場を回避するが、周囲の人との交流で自分の弱さを自覚し反省する成長の物語。心理状態も読み取りやすく、記号問題は高い正解率であろう。
例年、国立高校の小説文は女性作家の新刊作品から出題される傾向がある。今回も同様に2023年9月に出版されたオムニバス形式の短編集である。2026年度入試に備えるなら2024年後半から2025年前半期に出版された書籍を、特に今作のように「本屋大賞」にノミネートされた小説はチェックしておいてほしい。
【4】論説文(戸谷洋志「SNSの哲学」約4,100字、前年比+ほぼ変化なし)
「SNSは最適化のアルゴリズム(=処理手段)に支配されているが、現実世界は予見不可能な偶然性を前提に変化し続けている」という主旨の文章。今作品の書籍の副題にある「リアルとオンラインのあいだ」がテーマになっている。昨年に続き哲学分野の文章であるが、抽象論に終始せず適切な具体例を挙げているので中学生にも比較的読み取りやすい文章であった。
「確かに~しかし~」という「譲歩構文」の表現を問う問題など、従来あまり見られなかった傾向の出題もあった一方、国立高校では定番の抜き出し問題は今回も出題された。ただし、抜き出し問題は該当箇所を探し出すのに手間取るにちがいない。12点配点の200字作文も含め時間内で解答できるかどうかで他の受験生との差が付くだろう。
「哲学」は最近の入試の頻出テーマと言って良い。同筆者の近著「悪いことはなぜ楽しいのか」(ちくまプリマー新書)や藤田正勝著の「はじめての哲学」(岩波ジュニア新書)など、関連図書を是非ひもといておきたい。
【5】融合文(川本皓嗣「俳諧の詩学」約3,200字、前年比-約700字))
「去来抄」等を引用して松尾芭蕉の余情を重んじる姿勢を説いた文章。本文にもある「いひおほせて何かある(=言い尽くしてしまって何になるのか)」は、作句の要諦を示す芭蕉の言辞として他の文章で目にしたことがある受検生も多いだろう。すべて選択問題で比較的得点しやすかったと思われる。
お問い合わせ・お申し込み
-
イベント申し込みはこちら
-
資料請求はこちら