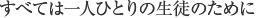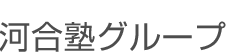八王子東高校問題分析 受験生情報局 | 河合塾Wings 関東
2025年度 八王子東高校の入試問題分析
八王子東の英語
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
【2】は語数に大きな変化はなく、内容も「人を助ける役割をもつ動物」に関する文章で、昨年と比較して読みやすいと思われる。昨年とは異なり、不適切な選択肢を選ぶ問題が出題されておらず、また、問3のような適語補充が出題されている。それ以外では同じ形式の問題となっている。内容一致の問題は論理的思考が身についていれば得点しやすいが、一方で問6の適語選択はやや難しい。選択肢の英単語の意味が分かるだけでは正解することができず、空欄の前後をしっかりと理解しつつ、入れるべき内容を判断しなければならない。英作文は「自分の10年後の姿」というテーマであった。「得意なことと関心のあること」の2つの観点を入れる条件が課されており、似たような内容を答えないようしっかりと区別しなければならない。また、単語数40語以上で答えなければならないため、意見や理由を考え付くよう慣れておかなければならない。
【3】も語数に大きな変化はない。【2】より文章量が多いため、時間配分には注意して解き進めていかなければならない。「ネットによる社会的比較」について書かれている文章で、身近な経験として想像しやすかったのではないだろうか。【3】も昨年と比べて問題形式に大きな変化は見られない。不適切なものを選ぶ問題が【3】に移っており、かつ3題の出題があるが、本文を理解できていれば難しくはない。問3の語句整序は、接続詞を用いた基本の連語表現をおさえていれば文構造が作りやすい。並べ替え該当箇所の前後がどのような語に続くのかということもあわせて確認すると良い。問4の適語補充は、答えの予測が簡単だが、「だれの視点にあわせて答えるべきか」を念頭に考えなければ失点するだろう。問2と問9では、一部の選択肢に難しい単語が含まれているが、問題レベルとしては正解したい。問8の適文補充は、代名詞や指示語を目印にしていくと正解にたどり着きやすい。全体的に目立った難問はないが、速読のトレーニングは変わらず重要である。また、やや難しめの語彙まで習得しておくこともカギである。
八王子東の数学
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
問題構成は大問1が小問4題、大問2~大問4は小問3題で、昨年度と変更はなかった。
【1】の小問集合は、例年どおりの難易度で計算等の基本的な力を問う内容であった。計算問題の計算量も例年と比べても多くなく、全問確実に正解したい。1は素数に含まれないことに注意が必要である。
【2】は座標平面上の放物線と直線に関する問題だった。問1は変域から値を求める問題で確実に正答したい。問2は三角形の面積に関する問題で、形式として見慣れない受検生も多かったかと思われるが、条件からtの条件をかなり絞れるので落ち着いて取り組めば正解にたどり着けるだろう。問3の記述問題は、台形と三角形の面積に関する問題で頻出問題である。日頃から類題をどれだけ解いていたかでスピードに差が出るだろう。
【3】は平面図形の問題だった。問1は基本問題。問2(1)の三角形の合同の証明は、具体的に長さを求めたりと少々珍しいパターンであったため、記述も多く苦戦した生徒も多いのではないかと思われる。問2(2)は正三角形の面積を求める問題で、条件から正三角形に気づけるかがポイントである。
【4】は空間図形の問題だった。問1は立体の表面上の最短距離の問題で、難易度としては易しい。問2は立体の体積の記述問題で、方針は立てやすいが、高さを求める方法に苦労した生徒が多いのではないだろうか。記述量も多いため、残り時間によっては部分点を取るために底面積を求めるだけでもいいだろう。問3は体積比を問う内容で、適切な補助線を引き、底面積の比から攻める頻出問題である。
八王子東の国語
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
【1】漢字の読み 10点 【2】漢字の書き取り 10点
【3】小説文 25点 【4】論説文 33点 【5】融合文 22点
出題形式・配点は昨年度と同様である。文章量は昨年と比べて全体で3,000字程度減少している。小説文・融合文は、難易度ともに同程度であるが、文章量が減少しているため多くの受験生にとって得点源になっている可能性が高い。そのため、記述問題・抜き出し問題もしっかりと解答し、得点に結び付けていく必要がある。また【4】の論説文は、文章量は減少しているが、【他者との関係性に関する文章】で昨年度よりも文章内容が難化していた。しかし、自校作成校の受験を考えている受験生は必ず目にするテーマではあるので、多くの問題に触れ慣れておく必要がある。
【1】、【2】(漢字の読み書き)
読みの「退いた(のいた)」・「放恣(ほうし)」は、中学生には馴染みのない言葉である。その漢字の訓読みや特に音読みができるかどうかが問われている。書きの「ヒッシ(必至)」は同音異義語で「必死」と書く受験生もいたのではないだろうか。また、「ゾウヒョウ(雑兵)」「リテイヒョウ(里程標)」といった、日常で接する機会が無い熟語が出題されるのは昨年と同様である。また、「退いた(のいた)」「アタり(辺り)」といった一字の訓読み、「鉄面皮(テツメンピ)」の三字熟語、「丁々発止(ちょうちょうはっし)」「イキトウゴウ(意気投合)」の四字熟語の出題は例年通りである。そのため、来年も出題されると予想されるため、対策が必要である。
【3】小説文(青山美智子「リカバリー・カバヒコ」約3,400字、前年比-約1,100字)
クリーニング店を閉めようとしている【母】とそれを止めようとする【息子夫婦】の【家族愛】を描いた作品である。例年、中学生・高校生を題材にした作品だったが、今年度は【家族】に焦点を当てた作品だった。受検生にとっては受験勉強の際に触れたことのある題材であると考えられ、登場人物の心情把握が中心の設問で、難易度はそれほど高くないといえる。ただし、50字の記述問題は、模範解答を見ると文章全体を読んだうえで書ける内容のため部分点は取れるが、満点の解答を書くのは難しいと考えられる。
【4】論説文(見田宗介「社会学入門」約3,500字、前年比-約500字)
「他者との関係性」ついて述べた文章。昨年度と比べると難化している。日常生活では目にしない語彙が文章中では使われており、語彙力の強化が必要である。しかし、よく出題されるテーマの文章であるため、解きづらいことはないと思われる。作文のテーマは、文章内容を理解したうえで、テーマに沿った作文を書かねばならず、昨年度のテーマの「日本と西洋の文化の差異」と比較すると難しい内容であったといえる。
【5】融合文(谷知子「古典のすすめ」一部改変 約2,200字、前年比−約1,500字)
和歌の幽玄の美に関する文章。幽玄は日本を代表する美的理念であるため、中学校の国語の授業でも扱われる。そのため、文章自体は読みやすい。各問において、直後にそれぞれの解説があるため解釈については難しいとはいえないだろう。昨年同様に語彙問題として「かきたてる」の意味が出題されたが、前後からも推測でき、昨年の「ほうほうの体で」よりは解きやすかった。また、昨年同様、問4では、抜き出し問題が出題されているが、口語訳に注目すれば解ける問題であった。全体的に平易な問題が多いことから、昨年に続き、この融合文で時間をかけずに高い正答率を出せるかが合格の一つの鍵であるといえる。
お問い合わせ・お申し込み
-
イベント申し込みはこちら
-
資料請求はこちら