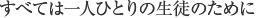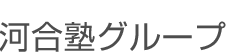青山高校問題分析 受験生情報局 | 河合塾Wings 関東
2025年度 青山高校の入試問題分析
青山の英語
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
今年度の青山高校は、【2】では対話文、【3】では物語文、【4】では自由英作文からの出題となり、大問構成に変更が見られた。また、例年と比較すると記述問題が大幅に増え、今年度は全体の6割の近くの点数を占める程にまでになった。大問構成や記述式の配点の多さなど、日比谷高校の入試問題と共通する点が見られた。
【2】は「個人での学習」と「集団での学習」についての対話文型の読解問題であった。問1、3の語句整序問題では知覚動詞や関係代名詞の知識を問う問題が出題されたが、基本的な内容であり確実に得点したい問題であった。問2では本文中3箇所に共通する語を補充する問題が出された。品詞への理解や熟語表現など多角的な視点で問題にアプローチする習慣が日頃から求められる問題と言える。また、平成30年度より出題されていた内容一致問題の出題形式は廃止され、一般的なものに変更されていた。全体を通して、空所前後や本文の流れを追う問題が大半であり、文章自体が長いものの、解答に必要な部分における精読力や要旨把握力が必要な問題であった。
【3】は「大切なものを人にあげる幸せ」についての物語文型の読解問題であった。筆者が友人から聞いた話と回想録の2部構成となっている。問1は、【2】と同様に、本文の複数個所に共通する語を補充する問題が出題された。beforeに関する複数の品詞理解が求められるため、日頃の単語学習の姿勢が問われた問題である。問2、問4、問5の内容把握問題は、下線部の前後情報を正確に読み取り確実に得点したい問題であった。問6では、友人が書いた日記の空所部分に、本文内容を踏まえて英作文をするという問題が出題された。友人との関係性や、コートの存在など、本文でどう定義されていたかを的確に表現する力が必要であった。
【4】では、「電子書籍」をテーマに、新たに自由英作文が単独で出題がされた。問1では、「電子書籍を読む生徒数の推移」のグラフから読み取れる内容を記述し、問2では、電子書籍と紙の書籍それぞれの利点を記述する問題であった。課されたテーマや求められる作文の難易度自体は平易ではあったものの、昨年までにはなかった出題形式だったため、解答の出来以上に「書けたかどうか」で点数の差の開きがあるように思われる。
例年と大きく異なる問題形式であり、時間配分や記述の方向性に迷う年だったと思われる。普段から様々なテーマの英文に触れたり、自分の考えやその理由を英語で書いたりと、中学の基本的な英語表現でのレパートリーを数多く増やしておくことで、英語の引き出しを増やしておくことが肝要である。
青山の数学
2025年度入試問題
難易度の表記
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
青山高校特有の問題文の誘導に従って解き進めていくという傾向は変わらず、全体的な難度も変化は見られなかった。よって例年通り、いかに問題を読み込んで意図を汲み取った回答ができるかどうかが合否を分けると考えられる。
【1】は例年通り、5題構成の小問集合。問3の確率は有理数という言葉の把握が必要であり、知識が試される問題であった。
【2】は例年通り関数からの出題であった。穴埋めかつ記述形式である問2に関しては問題の誘導にしっかり乗れるかが勝負のため、日々の勉強の中で多数の解法を身につけておくのが合格への鍵である。問3は一見難度が高いように感じるが気づけば速く解ける問題であるため、明暗を分ける1問になりうる。
【3】は例年通り平面図形からの出題。問1、問2は標準的な問題のため正答したい。問3は面積が等しい三角形を選び、その証明を行う問題である。中学2年生で学ぶ等積変形への理解度や練習量が要求されるため難問と思われる。このような難度の高い問題は飛ばして次の問題に進むという試験慣れをしているかどうかが重要である。
【4】は例年通り空間図形からの出題。問1は例年と比べ難度はやや高め。しっかり空間図形の見方を養っておく必要がある。問2は対話形式の問題であり、例年と比べ問題が複雑化された。そのため時間をかけて問題を読み込む必要があり、残り時間との勝負になると考えられる。問3は難度も高く、時間もあまり残っていないと考えられるため、飛ばした受検生は多いだろう。
全体的に文章量が多く、問題を正しく読み進める読解力、一つの解法に縛られない柔軟な思考力が必要と感じる入試であった。
青山の国語
2025年度入試問題
難易度の表記
青山高校を受験するなら
A:易問(全問正解したい)
B:標準問(受検者平均を取るために正解したい)
C:難問(差をつけるために得点したい)
D:最難問
問題分析
【1】漢字の読み 10点 【2】漢字の書き 10点
【3】小説文 22点 【4】論説文 36点 【5】融合文 22点
問題配点は昨年度と比べ、大きな差異はない。一方で形式の方は【3】以降の文章題の記述が増加している。
【3】~【5】まで記述がバランスよく配置されている形であり、試験時間をしっかりと考えて解く必要が例年以上にあった。加えて、全体の文章量は昨年と比べて2,000字強ほど増加している。特に論説文では、素早く要点をつかみ、筆者の主張を抑える力が求められた。しかしながら、選択問題などは昨年度よりも易化傾向であったため、多くの受験生が正解を出すのに一定以上の時間を要したとは考えづらい。
【1】、【2】(漢字の読み書き)
例年と比べ、比較的易しい。ただし、「滴(しずく)」という漢字は「雫」という字の方が中学生には馴染みがある可能性が高く、問題の「雨の滴が軒下に落ちる」を(主語・述語関係のもと)しっかりと読み、予想した受験生は正解にたどり着いたのではないかと考えられる。「シフク(至福)」については「至」の音読みを知らなかった受験生には厳しい問いであるといえる。
【3】小説文(上田健次「薬師湯」約3,600字、前年比+1,200字)
薬師湯という銭湯で手伝いをしている青年が、プラネタリウム鑑賞を通じて職人たちの生き方を改めて考える作品である。選択問題の難易度は比較的高くないが、昨年にはなかった記述が1題追加されている。文章全体から推測する問いになるため、満点の解答を出すのは困難だが、部分点を取ることは合格に必要であったと考えられる。
【4】論説文(保坂和志「世界を肯定する哲学」約4,000字、前年比+800字)
「宣言的記憶と非宣言的記憶(言葉によって伝達する記憶)」について述べた文章。昨年度と同等の難易度。単純な二者の比較ではなく、さまざまな記憶の種類が混在する整理が必要な内容となっている。選択記号問題は全体的に考えなくてはならないものも多く、易しい問いではない。また、作文のテーマは文章内容を理解したうえで、テーマに合うように記述する必要がある。特段書きづらい内容ではないものの、字数の増加による時間配分が決め手となる。
【5】融合文(若山滋「文学の中の都市と建築」約3,150字、前年比+150字)
枕草子の空間的な美について述べている文章。枕草子は日本を代表する文学作品であり、学校の教科書にも登場するので、文章のイメージはとらえやすい。各問において、前後にそれぞれの解説があるため、理解が追いつかないことはないだろう。ただ、「はばかられる」や「花鳥風月の情景」など語彙的な要素でつまずく可能性はある。前後に書かれている内容を要約し、端的に理解していくことが求められる。
お問い合わせ・お申し込み
-
イベント申し込みはこちら
-
資料請求はこちら