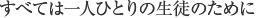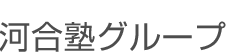サイエンス講座案内 講座案内・時間割 | K会 春期講習
各講座の詳しい内容をご紹介します。
K会の教室窓口ではテキストもご覧いただけます。講座選択にあたってご参考になさってください。
【情報】情報科学講座入門~新中1生対象~
受講目安
新中1生を対象としたK会レギュラー講座「IS1」への入門講座です。興味のある新中1生の方であればどなたでもご受講いただけます。
講座内容
プログラミングとは、コンピュータに依頼する仕事を書き出した指示書のようなものです。ただし、コンピュータは人間の言葉を理解することができないため、「プログラミング言語」と呼ばれる専用の言葉を用いなくてはいけません。PythonやC++といったプログラミング言語を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。本講座ではJava言語をベースにした初学者にも扱いやすいProsessingという環境で、みなさんにプログラムを「書く」経験をしていただきます。まず、足し算する、数を覚える、繰り返すといった基本となる指示の書き方を、練習問題を交えながら学習します。同時にタイピングの練習やコンピュータの仕組みといったプログラミングをするうえで大切なことも身に付けていきましょう。最終日には学んだことを用いて、ボールを動かすゲームや、花火などの簡単なアニメーションを作ることが目標です。難しそうだなと不安に思うかもしれませんが、授業は10名以内の少人数で、講師が巡回しながら一人ひとり丁寧に指導をします。いつでも質問ができる環境です。疑問はその都度、講師と一緒に解決しながら進めていきましょう。本講座がK会のIS1講座の入門としてはもちろん、プログラミングに親しむきっかけとなれば幸いです。※パソコンは一人一台ご用意しています。
テーマ
第1講 プログラミング入門
第2講 for文をマスターしよう
第3講 配列をマスターしよう
第4講 ゲーム作り
このようなことを学習します
コンピュータの強みは何といってもその計算の速さと正確さです。まずは小学校で習う「四則演算」をコン ピュータに計算させてみましょう。その後、円を動かすアニメーションなどにも挑戦していきます。
- 日程
-
3月28日(金)~3月31日(月)
- 時間
-
10:00~13:10
- 講座コード
-
S211
- 講師名
-
森 裕淳
【情報】Pythonではじめるプログラミング入門
受講目安
興味のある中高生の方であれば、どなたでもご受講いただけます。K会レギュラー講座「IS1」の入門としても最適です。
講座内容
本講座では、Pythonというプログラミング言語を用いて、プログラミングの基本的な技法を学習します。今回使用するPythonという言語は、インターネット上で動作するWebアプリケーションや画像加工、AI(機械学習)、科学計算など、幅広い分野で実際に使われている言語です。コンピュータはプログラムに書かれた命令をそのとおりに実行しますが、その中身は「足し算する」「数を覚える」「繰り返す」といった単純なものからできています。本講座では、このような命令の書き方を練習問題を交えながら重点的に勉強します。最後には覚えた知識を組み合わせて、「地名を入力すると天気予報を表示する」「数学の方程式を入力するとその解を表示する」など、オリジナルのアプリケーション作成に挑戦します。制作したプログラムは持ち帰りが可能です。授業中は講師が巡回しながら一人ひとり丁寧に指導しますので、初めての方でも安心してご受講いただけます。K会の情報講座を通じて、さまざまな知識や技法を習得し、今後のパソコン学習や学校生活にお役立てください(パソコンは一人一台ご用意しています)。
テーマ
第1講 プログラミング入門・if 文
第2講 for 文・リスト
第3講 関数・モジュール
第4講 アプリケーション作り
時間割・担当講師
- 日程
-
4月2日(水)~4月5日(土)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講座コード
-
S331
- 講師名
-
石川 竜聖
【情報】3DCGに挑戦!
受講目安
プログラミングの経験がある方(if文、for文などがわかる方)を対象とします。
講座内容
3DCGはコンピュータを用いた立体的な画像生成技術のことで、映画やゲームの映像作成、VR、ARアプリケーションなどに用いられています。また、3DCGは立体的な設計をするための3DCAD(computer aided design)内部でも活用されています。本講座では、3DCGの仕組みを理解し、Processingを用いて実際に3DCGの作成にチャレンジします。Processingはあまり耳なじみのない言語かもしれませんが、とても実用的で、プログラミングで新しいことを学ぶのに最適な言語です。本講座では、まず3DCGの基礎的な内容を学習し、3D物体の描画と移動の実装を行います。次にシミュレーションによるCG作成について学びます。最後に、これまで扱った内容を組み合わせて、3DCGを使ったゲーム作成に挑戦してもらいます。アニメーションやモデリングに興味のある方にはおすすめの講座です。講座内で文法などを解説しますので、Processingを使った経験がなくてもご安心ください。if文やfor文、変数、配列といった基礎的なプログラミングに触れたことがあればどなたでも歓迎いたします。
テーマ
第1講 Processingの基本
第2講 3DCGを描いてみよう
第3講 シミュレーションCG
第4講 3Dゲームに挑戦
- 日程
-
3月23日(日)~3月26日(水)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講座コード
-
S131
- 講師名
-
瀬戸 友暁
【物理】物理学入門
受講目安
中学数学について一通り理解している方を対象とします。
講座内容
みなさんは“エネルギー”という言葉を聞いて何をイメージするでしょうか?おそらく多くの方は、その言葉を聞いて何かしらのイメージが浮かんで来るでしょう。では、物理学においての“エネルギー”とは何を指すのでしょうか?本講座では、中学や高校の理科を超えて、物理学の本質を理解することをめざします。そのために、まず、物理学の理論を理解するために必要な微分・積分などの数学を扱います。その後、主に力学を中心に、運動量やエネルギーといった概念について講義と演習を通してじっくりと学んでいきます。実際に自分の手で計算し例題を解くことで、概念を習得するだけではなく、数学がどのように物理学に応用されているのかも学ぶことができるでしょう。本講座は、物理学への入門であると同時に、4月から始まるK会のレギュラー講座の入門でもあります。物理学を学ぼうとする意欲的な方や既に学校で物理を学んでいて本格的な理論を学びたい方、 さらにはK会への入会を検討されている方まで、 多くの受講生の方をお待ちしています。
テーマ
第1講 前提となる数学
第2講 運動の3法則、ニュートンの運動方程式
第3講 運動量、エネルギー
第4講 発展的なテーマ
- 日程
-
3月28日(金)~3月31日(月)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講座コード
-
S231
- 講師名
-
粟野 稜也
【物理】物理チャレンジへの一歩
受講目安
前提知識は必要としませんが、高校物理基礎の知識があると、よりスムーズに講義を理解できます。
講座内容
物理チャレンジは高校生以下が参加できる物理の全国大会で、毎年1,000人ほどが参加しています。こう書くとハードルが高く見えてしまいますが、実際は全問題が高校までの知識で十分解けるような内容です。定期試験や受験勉強では見慣れないテーマも出題されますが、リード文に必要な情報がすべてあり、小問を1問ずつ解いていくことで理解できる構成になっているので心配は無用です。むしろ、高校では扱わないさまざまな物理の話題に触れることができるので、物理が好きな方にはおすすめです。また、高校2年生以下の方は良い成績を収めると国際物理オリンピックの代表候補になることができます。本講座は、物理チャレンジの予選にあたる、1次チャレンジの突破を目的とした講座です。1次チャレンジは90分間のマーク式の理論試験と、与えられたテーマで実験を行いレポートを作成する実験課題レポートからなります。前半は、評価されるレポートの書き方、コツなどを伝授し、後半では過去の理論試験の問題を抜粋して傾向や対策などを解説します。物理チャレンジで実績のある講師が自身の経験をもとに効率よく講義します。物理チャレンジに興味を持っている方から、物理が好きな方まで、幅広い参加をお待ちしています。
テーマ
第1講 物理チャレンジの概要、実験レポートの書き方
第2講 理論試験
時間割・担当講師
- 日程
-
4月2日(水)・4月3日(木)
- 時間
-
10:00~13:10
- 講座コード
-
S311
- 講師名
-
揚妻 慶斗
【化学】化学グランプリに挑戦してみよう
受講目安
原子、分子、元素、価電子、共有結合、イオン、分子量、物質量(mol、モル)の概念と、文字式の四則演算、簡単な指数対数の計算を理解している方を対象とします。イオン、酸と塩基、有機化合物の立体配置について簡単な理解があると、よりスムーズに講義を理解できます。
講座内容
毎年夏に開催される「化学グランプリ」は、日本全国から参加する中高生が化学の思考力と技能を競う大会であり、高2以下の優秀者は次年度の国際化学オリンピックの日本代表候補にも選ばれます。化学グランプリでは海の日に一次選考の筆記試験が、8月に二次選考の実験試験が行われます。本講座では2023年の筆記試験の問題を取り上げ、皆さんに実際に問題を解いてもらいながら解説します。化学グランプリでは大学レベルの内容を取り扱いますが、中高生の知識で解けるように解説と誘導がなされるのでそれをもとに考えて解き進めることができます。その中でも2023年度の問題では、日本の産業を支えるヨウ素やケイ素の興味深い化学を味わうことができます。例年と傾向の違う問題が多く、過去の受講者も楽しめる内容です。高校までの範囲で高校では触れる機会の少ないトピックを垣間見させてくれるのが化学グランプリの筆記試験の醍醐味でもあります。講義のスムーズな進行上、受講目安に述べた内容を一通り理解していることが望ましいですが、多少の不足分はサポートできますので気兼ねなくご参加ください。化学グランプリ対策だけでなく、化学について普段触れない内容に出会い楽しく学ぶ機会にもなります。
- 本講座は毎回異なる問題・テーマを扱います。以前受講された場合も、今回と内容は重複しません。
テーマ
第1講 基礎化学の問題
第2講 物理化学の問題
第3講 無機化学の問題
第4講 有機化学の問題
時間割・担当講師
- 日程
-
4月2日(水)~4月5日(土)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講座コード
-
S332
- 講師名
-
吉田 悠真
【生物学】病態生理学入門~生物学オリンピックと医師国家試験を題材として~
受講目安
興味のある中高生の方であれば、どなたでもご受講いただけます。
講座内容
生理学とは、生体のメカニズムを分析し理解する学問です。生体は器官系(循環器系、呼吸器系、消化器系、泌尿器系、運動器系、神経系、感覚器系、内分泌系、造血・免疫系、生殖器系など)から構成されており、器官系は器官(心臓、血管、肺、気管支、消化器、肝臓など)から構成されており、器官は組織(上皮組織、結合組織、筋組織、神経組織)から構成されており、組織は生命の最小単位である細胞から構成されています。このような階層性のある構造が特定の機能を果たすために協働することで、生体の内部環境はほぼ一定に維持されています(ホメオスタシス)。このホメオスタシスが破綻すると「病気」と呼ばれる状態になりますが、正常の生体機能のメカニズムが破綻する原因(病態生理)がわかっていれば、それに基づいて診断方法や治療方法を考えることができます。本講座では、第1講で主に生物学オリンピックの問題を通じて生理学の基本事項を解説します。第2~4講で医師国家試験などの症例問題のディスカッションなどを通じて「どのような機能がどのように破綻すると、どのような疾患が生じるのか」という臨床推論の考え方を体験していただきます。中学校の理科や保健で習う事項をさらに深めていくことで実際の医学に繋がっていく様子を眺めてみませんか。
テーマ
第1講 生理学入門
第2講 循環器/呼吸器
第3講 腎・泌尿器/消化器
第4講 内分泌・代謝
時間割・担当講師
- 日程
-
3月28日(金)~3月31日(月)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講座コード
-
S232
- 講師名
-
熊谷 勇輝
【生物】遺伝学入門 ~生物学オリンピックと医師国家試験を題材として~
受講目安
興味のある中高生の方であれば、どなたでもご受講いただけます。
講座内容
「カエルの子はカエル」ということわざは、一般に「子は親に似る」という意味で使われます。しかし、なぜ子は親に似るのでしょうか。そもそも、なぜカエルの子は、ウマやライオンではなく、やはりカエルになるのでしょうか。この素朴な疑問の背後には、「遺伝」という非常に奥深いメカニズムが存在します。本講座では、細胞から個体、そして集団へと視点を移していきながら、遺伝学の基礎から応用まで体系的に理解することをめざします。第1講では、細胞生物学の初歩に触れ、細胞構造や染色体、DNAといった「遺伝の舞台」を明確にします。第2講では、中学校の理科で学ぶメンデルの法則から始めて、生物学オリンピックや医師国家試験の問題を題材に、古典遺伝学の計算や思考法をパズルのように楽しみながら学んでいきます。第3講では、分子遺伝学の視点からDNA、転写・翻訳、遺伝子発現制御の仕組みを学び、遺伝子操作やPCRなどの技術がどのように研究や医療で応用されるかも概観します(実習は行いません)。第4講では、Hardy-Weinbergの法則、自然選択、遺伝的浮動などの集団遺伝学の基本概念を理解し、疾患の集団レベルでの解析などにどう繋がるのかも考えていきます。この4日間で21世紀の遺伝学を学ぶための第一歩を踏み出してみませんか。
テーマ
第1講 細胞生物学
第2講 古典遺伝学
第3講 分子遺伝学
第4講 集団遺伝学
時間割・担当講師
- 日程
-
3月23日(日)~3月26日(水)
- 時間
-
17:30~20:40
- 講座コード
-
S132
- 講師名
-
熊谷 勇輝
【地理】概説・地理の世界 〜地理的思考を身に付けよう〜
受講目安
興味のある中高生の方であれば、どなたでもご受講いただけます。
講座内容
「地理」とは、一言でいうと、「《地域》という視点から事象を考察し、記述する」教科だということができます。その意味で、あらゆる事象が「地理」での考察対象になる、ということもできるでしょう。それくらい地理はダイナミックであり、同時に身近な教科・学問です。本講座では、そうしたさまざまな事象を、さしあたり「人間」「自然」「人間と自然」という3つの切り口から捉え、地理という教科の全体像を眺めてみたいと思います。その際には、「なぜこのような気候になるのだろうか?」「なぜ人々はそこでそのような産業を営むのだろうか?」「どうしたらこの都市が抱える問題は解消するだろうか?」といったさまざまな「なぜ?」や「どうして?」を大切にし、それらに対する答えを的確に言語によって記述する、という作業をすることによって、また、写真や図表を読み解く、という作業を通じて、「“地理的な”思考法」を身に付けることにも挑戦します。これから地理の学習を始める方には、その道標として、これから地理オリンピックをめざす方やアカデミアで地理に関係する分野を修めることをめざす方は、その土台づくりとしてご活用いただけます。大切なのは、素直に頭を働かせることと、きちんと記述することです。予備知識は必要ありません。この分野に興味のある新中1生から高校生までの幅広い参加をお待ちしています。
テーマ
第1講 自然地理
第2講 人文地理①
第3講 人文地理②
第4講 地誌
時間割・担当講師
- 日程
-
3月28日(金)〜3月31日(月)
- 時間
-
17:30〜20:40
- 講座コード
-
S233
- 講師名
-
佐藤 弘康
【地学】地学を概観する~地球と宇宙の壮大な旅路へ~
受講目安
興味のある中高生の方であれば、どなたでもご受講いただけます。
講座内容
地学という学問分野は、地球の中心から宇宙の彼方まで、宇宙の開闢から遠い未来までを対象として扱う、極めて壮大な学問です。本講座では、こうした壮大さを念頭に置きながら、地学としてくくられる分野を幅広く扱います。最初に地球の形や構造についての簡単な知識をつけたら、いよいよ地表面から地下へ、そして地球の中心へと旅を進めていきます。硬く静的に思われる地下世界が、実はダイナミックな動きに満ちていることを垣間見ることができるでしょう。ひと通り地下世界を見回ったら、地上へと戻り、大気や海洋を見回ります。流動性に富む大気や海洋は、私たちが十分に観測できる時間スケールで、多種多様な現象を提示してくれます。今度は時間軸に沿って旅をしましょう。地球誕生から現在の地球へ、そして未来の地球へと、地球の歩む道のりを追っていきます。道中、蒸し風呂のような地球や凍てついた地球など、さまざまな地球の姿を見ることができるでしょう。最後はいよいよ地球を脱出します。宇宙を時間軸・空間軸に沿って縦横無尽に駆け巡りながら、地球とは比べ物にならないほど極端な現象の数々を見ていきます。さあ、地球と宇宙の壮大さを垣間見る旅に出かけましょう!
テーマ
第1講 地質・固体地球-地球中心への旅-
第2講 大気・海洋-躍動する地球表層-
第3講 地球史-地球の過去・現在・未来-
第4講 天文-太陽系から宇宙の彼方へ-
時間割・担当講師
- 日程
-
4月2日(水)~4月5日(土)
- 時間
-
14:00~17:10
- 講座コード
-
S321
- 講師名
-
中尾 俊介
【言語学】言語学オリンピックで入門する言語学
受講目安
興味のある中高生の方であれば、どなたでもご受講いただけます。
講座内容
みなさんは「言語学オリンピック」をご存知でしょうか。「何種類の言語を話せればいいの?」「人文科学の能力をどうやって順位づけするの?」と思われる方も多いでしょう。実は、国際言語学オリンピック委員会は「言語学や言語に関する知識は必要なく、最も難しい問題であっても論理的思考力や忍耐強い努力、常識に囚われない発想力があれば解ける」と述べており、日本委員会でも「問題は実際の言語研究で行われる分析に似ていて、『初めて見る言語のデータから隠れた法則を解き明かす』というものです。謎解きやパズルのように、分析力、情報処理能力、論理的思考、試行錯誤する力が求められます。この点で、数学やプログラミングと根本となる能力が似ていると思われます」と述べられています。この講義では、言語学オリンピックの初歩的な問題をゆったりと扱いながら、一歩ずつ着実に言語学の考え方に慣れ親しんでいただくことをめざします。学校で教えられる日本語や英語の伝統的な文法の捉え方も変わってくるような刺激的な問題をぜひ解いてみませんか。
- 昨年度から内容を一新し、 初学者の方により親しみやすい内容となりました。
テーマ
第1講 答案の書き方
第2講 音声学
第3講 音韻論
第4講 形態論
時間割・担当講師
- 日程
-
3月28日(金)~3月31日(月)
- 時間
-
14:00~17:10
- 講座コード
-
S221
- 講師名
-
小林 剛士
【天文学】天文学を概観する ~天文学オリンピックを通じて~
受講目安
指数・対数の基礎知識を必要とします。
講座案内
空に浮かんだ星たち、美しい銀河や星雲…みなさんも1度はこのような写真を、もしくは自分の目で見たことがあるでしょう。これらの天体は天文学が扱う1つのテーマです。本講座は、天文学オリンピックで出題された問題を題材に、天文学とはどのような学問であるか、その枠組みを捉えることを目的としています。天文学オリンピックとは、2022年に第一回が開催された天文学の知識・思考力・技能などを問う大会です。日本の中学校や高校ではあまり詳しく扱われない天文学ですが、そのスケール感や美しさなど魅力にあふれた学問です。本講座ではまず、天文学における現象によく現れる古典力学や、輻射やHR図といった天文学ならではの話題を扱います。次に、天球の座標や時刻といった概念を扱います。空に浮かぶ星の位置を正確に記述する方法や、1日や1年がどのように決められるか学びましょう。そして最後に天体を観測する方法や星座などの話をします。天文学は観測によって発展してきた人類最古の学問です。その人類の技術の結晶である観測機器や、特徴のあるさまざまな天体のおもしろさを感じましょう。本講座を通して、天文学の枠組みを作り、基礎を正しく理解することで新たな現象を自分で考えることのできる力を身につけることができるはずです。
テーマ
第1講 古典力学
第2講 輻射の基礎/HR 図
第3講 天球の座標/時刻
第4講 観測機器/さまざまな天体
時間割・担当講師
- 日程
-
3月28日(金)~3月31日(月)
- 時間
-
10:00~13:10
- 講座コード
-
S212
- 講師名
-
早川 晴
【数学×物理】Fourier 級数論
受講目安
中学数学について一通り理解している方を対象とします。
講座内容
数学や物理学では、関数の振る舞いを調べることが重要です。そのため、調べたい関数を、すでによくわかっている関数の組み合わせとして表すことは非常に有用です。たとえば、多項式の“和”として表すTaylor級数や、三角関数の“和”として表すFourier級数などが開発されてきました。本講座で扱うFourier級数論とは、少なくとも古典的には、「どんな関数も必ず三角関数の“和”(Fourier級数)で表せるか?」というテーマを探究する分野だと言えます。第1講と第2講では高校程度の三角関数と微積分を速習し、第3講ではFourier級数の計算に慣れてからDirichletの定理を証明します。また、Fourier級数によって等周問題が解決できたり、数論で非常に重要なRiemannゼータ関数の正の偶数に対する特殊値(特にBasel問題)が計算できたりと、数学上の幅広い応用が可能であることを実感します。第4講では、Fourier級数が微分方程式に応用できること、したがって物理学(力学、熱力学、振動・波動論、量子力学など)に応用できることを学びます。基本的な中高数学の計算によって、数学や物理学への華々しい応用が得られる様子をぜひ実感してみませんか。
テーマ
第1講 三角関数
第2講 微積分
第3講 Fourier 級数
第4講 物理学への応用
時間割・担当講師
- 日程
-
4月2日(水)~4月5日(土)
- 時間
-
10:00~13:10
- 講座コード
-
C311
- 講師名
-
熊谷 勇輝
-
資料請求はこちら