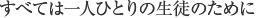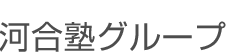激突!現役生VS高卒生 ー直前期の「現役生追い上げ」は果たして都市伝説かー 知っ得!医学部合格の処方箋 知っていますか?~知識編~ | 知っ得!医学部合格の処方箋 | 医の知の森<近畿地区医学科進学情報センター>
現役合格への道、三つの要素とは?
「最大パフォーマンス」を本番で発揮できるかどうかは、自分の心がけにかかっています。模試やテストでつまずきがあるなら、自分の日頃の心がけを見直すチャンスです。
医学部受験生に目立つ「積極浪人」
過去20年ほどの間、大学は新設や学部増設などで入学定員を増加させてきました。その一方でここ数年、18歳人口が減少したことで大学入試の倍率は全体として低減し、入試難度は緩和しつつあります。医学科の難度も多少の影響を受けていますが、工学部など定員の多い学部ではその影響がより顕著に出ています。
入試倍率低減の影響で大学に合格しやすくなったため、当然「高卒生」(いわゆる浪人生)の人数は減少しています。それでも、医学部受験生には浪人する人が少なくありませんし、以前にも増して「積極浪人」が割合的には目立ってきました。「積極浪人」とは、いずれかの大学合格が出ていながら、あえて浪人を選択する人たちのことをさします。
「積極浪人」のうち、合格した大学に「手続きせずに浪人を選択した人」たちは「合格浪人」と呼ばれています。私立大医学部に合格しても国公立大医学部の合格を目指して浪人するパターン、併願合格が医学部以外だったため入学を見送ったパターンなど、人によって状況は様々です。
また「大学に籍を持っていながら浪人する人」もおり、こちらは「仮面浪人」と呼ばれています。合格している大学に手続きし、籍を確保しつつ実質的に浪人する人たちです。こうした方々は医学部以外の学部の籍を持っていることが普通です。かつて私が見てきた中では、旧帝大の工学部や歯学部に籍を持ちながら医学部を目指す人が多く、中には東大に籍があった人までいました。
医学部を目指す高卒生は、「積極浪人」ばかりではありませんが、比較的それが多いのは事実です。入試で一定の成果を出した「積極浪人」たちは、現役生にとって大きな脅威となるでしょう。
現役生の合格への道
ここでいよいよ本題です。現役生はどのようにして高卒生に対抗し、合格に到達することができるのでしょうか。現役生と比較して高卒生の何が違うのか…、その考察をしつつ現役生の対応策を考えてみましょう。
高卒生が現役生よりアドバンテージがあることは二つあります。まず一つめは基本的に各科目の「学習範囲はある程度演習してきている」こと、二つめは受験直前期〜受験期を経ているので、「学習習慣がある程度確立している」ことです。
私が「ある程度」というのは、高卒生たちはそれが不徹底だからこそ「浪人」した可能性があり、現役時代には完璧でなかったと思われるからです。それでも一度受験期を経ていれば、さすがに4月以降の新年度をスタートする際には、ロケットスタートのように学習を始めることができるでしょう。そこで、現役生が高卒生に対抗するためには、そういう高卒生の状況を頭に入れておかなくてはなりません。
「現役生の高卒生対応策の一つめ」として、高卒生のようなロケットスタートをしようとせず、「時間を無駄にしないように徐々に演習を重ねること」と心得ておくことです。年度の前半で高卒生と差があっても「今はまだいい…」と自分を落ち着かせ、自分の手元にある教材を徹底して活用し、「徐々に演習を進めて追いついていこう」と強い気持ちを持ち続けてください。
一部の中高一貫校は5月くらいに全部の学習範囲を終わって演習を始めているため高卒生に比較的近い状況ですが、それでもまだまだ演習は足りません。公立高校の人なら学習範囲がまだ終了していないものがありますから、より演習不足をつよく感じるはずです。
受験学年は何かと焦りが出るものですから、気持ちのコントロールはとても重要です。強い気持ちが持てていないために、焦って自分の実力に合わない問題集に手を出し、空回りして時間を浪費する人を私はたくさん見てきました。そういうことがないようにしていきたいものです。
「現役生の高卒生対抗策の二つめ」は、「確立された学習習慣」を作ることです。「別に今でもやっているのに…」という声が聞こえてきそうですが、ご自身の学習は本当に受験生として理想的なのでしょうか。例えば自習室であなたが友人たちと一緒に「今日の復習」と「明日の予習」をしていると、友人の方が早く終わってしまうことはありませんか。それはどうしてなのでしょうか。
ヒントとして、こんな話はどうでしょう…。かつて2つのクラスで授業アンケートをとったところ、片方のクラスは「はじめてください」というや否や、まるでテストのように最速でアンケートを記入してあっという間に終わらせてしまいました。ところが、もう片方のクラスでは「えーっと…」などとのんびりと記入し、時間内にまだ終わっていない人まで出る始末です。そういう人たちの言い訳はいつも決まっていて、「アンケートなんてテストじゃないんだし…。まぁ、やる時はやりますから…」というものです。しかし、模試を「やる時」だと考えると、その言い訳は当たっていませんでした。当然、成績は前者のクラスが上…「生活習慣に無駄がない→学習時の集中力向上→理想の学習習慣確立→成績(学力)上昇」ということなのだと思います。
あなたが4時間かけて完了することを、友人は3.5時間で終わってしまうということです。あなたは入試ではないからとのんびり計算していたり、ゆっくり英文を読んだりしていませんか。一方で友人は、最速で計算し、最速で英文を読むことが習慣になっているのではないでしょうか。それが0.5時間の差になって現れるということです。音楽を聴きながら学習している人が最近は増え、集中力を日常で発揮する訓練が不足しています。「ながら学習」が癖になってしまうと自ずと学習集中力は欠如し、いつまで経っても本物の集中力を身につけることはできないでしょう。私からは、本物の「確立された学習習慣」を身につけるよう、現役生にご提案します。
受験学年の1学期に「この二つ」を念頭に学習を継続し、最大集中力を発揮できる状態を1学期に作り上げ、「夏休みの学習期間」に接続しましょう。夏休みいっぱいの1カ月の間に、「最大パフォーマンス」の学習を発揮することができれば大きく前進することができるに違いありません。
よく「高3の秋から学習をスタートして失敗した、それでは遅かった…」という話を聞きます。皆さんは、「それはそうだろう」程度に単純に考えていませんか。少し深読みすると、おそらくそういう失敗した受験生の方々は、本当に「秋にゼロからスタート」したのではないと思います。本当は夏休みから学習をスタートしたのでしょうが、夏の間に最大集中力を発揮する訓練をしなくてはならなくなってしまい、できたりできなかったりをくりかえした…。その結果、自分の「最大パフォーマンス」を日々の学習で発揮できるようになったのが秋だった…といっているのではないでしょうか。
ですから、その訓練を一つ手前の「1学期」にすることによって、夏に「最大パフォーマンス」のピークを持っていこうというのが私のご提案の趣旨です。「やる時はやる」と豪語した生徒が直後の模試で実力を発揮できなかったように、「日頃の訓練」をしていないと、すぐに「最大パフォーマンス」を発揮することはできません。1学期に集中力を発揮する訓練をし、夏に現役生が最大の集中力で演習を重ねることができれば、入試直前期にその積み重ねをアウトプットできるようになるはずです。
直前期に成績上昇するのは現役生
データを少しみてみましょう。これは河合塾に通学しているある地区の高卒生と現役生の共通テスト型模試の総合平均点を年間で見たもので、グラフの最終は共通テスト本試験です。高卒生は当然平均点が高いので、常にグラフが上側になっています。しかし、5月の段階では100点もの差があった高卒生と現役生ですが、本番では一気に平均点が上がり、その差が40点ほどになっています。
<グラフ1>
このグラフからは、直前期に一気に追いつこうとしている現役生の姿が見て取れます。おそらく、模試の判定でも直前期に近づくまでは「E判定」や「D判定」がまだ連続していたに違いありません。年度スタートの段階では、自分の学習は「時間を無駄にしないように徐々に演習を重ねること」だと強い気持ちで言い聞かせ、最大集中力を発揮する「確立された学習習慣」を作り上げようとする強い気持ちが、本番での成果に結びついていくといえるのではないでしょうか。
1点に10人〜15人が並ぶような医学科入試では、「最大パフォーマンス」を本番で如何に発揮するかが鍵です。現役生が直前期に成績を伸ばせることは、このグラフを見てのとおりです。このグラフは医学科志望以外の人も含んでいますから、あとは現役で医学科を目指す皆さんがこのグラフ以上に高卒生に肉薄する成績を出すことでしょう。
「やる時はやる」というなら、それは今日です。そして今です。「最大パフォーマンス」を本番で発揮できるかどうかは、自分の心がけにかかっています。模試やテストでつまずきがあるなら、自分の日頃の心がけを見直すチャンスです。
現役合格のための三つめの要素
ある格言があります。
「多くの人はつまずくと靴や道路を見る。しかし、靴や道路があなたをつまずかせたのではない。人はなかなかつまずきを自分のせいにしない」
そういわれると、どう思いますか。ある人は「なるほど」と納得しますが、「そんなことはわかっている…」という人もいるでしょう。それぞれの人の感性があるはずです。
かつて多浪生が私に「これだけは現役生に負けていた」と伝えてくれたもの、「これがなかったせいで合格に何年もかかった」と彼がいっていたもの、それをこの格言が示しています。現役生が諦めずに学習を継続することができ、学習することに意味や価値を与えてくれる源であり、現役生が高卒生に勝つために必要なもの…。それは「謙虚さ」です。
「見たことのある問題」を「できる問題」に変換してしまうような、「謙虚さの欠如が自分を多浪にしてきた」と多浪生の彼は私に伝えてくれたのです。
「謙虚さ」は本人の生き方に関わる「想念状態」そのもの、日頃の心がけや物事への取り組み姿勢の源といってもいいでしょう。そこに「現役生の合格への道」の最後の手がかりがあります。年度当初のアドバンテージで鼻高々な高卒生を直前期に退ける「現役生の高卒生対抗策の三つめ」を発揮させられるかどうか。それは受験生本人の「謙虚さ」、その人の「生き方そのもの」にかかっているのです。