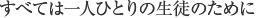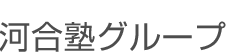変わる新大学入試の対策について、河合塾の英語講師がわかりやすく解説! コース・講習
2021年1月から「大学入学共通テスト」が新しく始まります。
ニュースなどで報道されている通り、2021年度入試においては、「大学入試英語成績提供システム」の導入見送りが、文部科学省から発表されました。「大受入試はどうなるんだろう」「どんな対策をしたらいいの?」と不安を感じている方も多いはず。そんな高校生・高卒生の皆さんの疑問に、河合塾の英語科講師がわかりやすく答えます!
新しくスタートする「大学入学共通テスト」は、「知識・技能」に加え「思考力・判断力・表現力」が問われる出題になると言われています。しかし、これらを問う出題は、難関大学では以前から当たり前のように出題されており、この方向性が再確認されるということです。
目先の変化に惑わされず、早いうちから基礎的な英語力をしっかり身につけることが大切です。
(1)発音、アクセント、語句整序などを単独で問う出題はなくなります。
センター試験では、始めに「発音・アクセント」、「語句整序問題」が出されるのがおなじみでしたが、これはなくなります。「筆記」は「リーディング」に改称され、文章や文献など複数の資料から概要を把握する力、情報を読み取る力などを問うことをねらいとし、ほとんどが長文読解に近い問題になります。
(2)「リーディング」と「リスニング」が同配点になります。
センター試験での配点では、【筆記】が200点、【リスニング】が50点でしたが、大学入学共通テストでは【リーディング】100点、【リスニング】100点の同配点になります。今まで以上に、リスニングはしっかり対策していく必要があります。
(3)「リスニング」では1回しか読み上げられない問題も
センター試験ではリスニングの音声は必ず2回読み上げられていましたが、共通テストでは、問題によって1回読みと2回読みが混在するようになります。
さらに、1回のみ読み上げられる音声を聞いて、ワークシートを作成する問題や、聞き取った内容と資料やグラフをあわせて読み解く問題、リスニングで文法を問う問題など、慣れていないと本番で慌ててしまいそうな問題も出されます。
新しい大学入試では、英文を英文のまますばやく理解し解答するという“反射神経”も求められます。ポイントは、文章の趣旨・要旨を読み取ることです。設問の意図は何か、各パラグラフではどんなことを伝えようとしているのか、丁寧に考えながら英文を読む、これを普段から意識して、すばやく読めるように訓練を重ねていくことです。
新しい大学入試の傾向として、音声問題が増えることは確実です。英語の“音”に慣れるにはそれなりに時間がかかるので、できるだけ早くから対策を始めることが必要です。特に高1・2生は、普段から“音”を意識した学習を心がけましょう。たとえば、英単語を覚える場合にも、(1)音を知る、(2)スペルを知る、(3)意味を知る、(4)用例を知る、というように“音”に意識を向けることです。
「大学入学共通テスト」が新しく始まりますが、まずは基礎固めが大切です。大学受験に照準をあわせた良い教材を使って、揺るぎない英語力を身につけましょう!
河合塾のテキストなどの教材は、受験のプロが「これができれば大丈夫!」という知見をすべてつぎ込んでつくられています。早いうちから新しい出題形式の問題を含む質の高い教材に触れておけば、受験本番で周りに大きな差をつけられます。一緒に、新しい大学入試を勝ち抜きましょう!
-
高校生対象
-
高卒生対象
-
高校生対象
-
高卒生対象